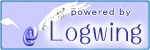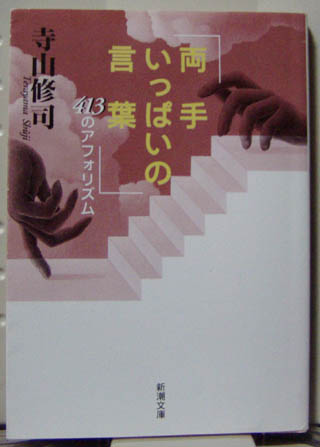
amazonのデータはこちら
横浜の三浦投手にそっくりの寺山修司――というのは置いておくが、『「名言集は言葉の貯金箱なのね」と言った女の子がいる。そうかも知れない。』という文句ではじまっているこの本は、寺山修司の本、映画、劇作など色々の著作から、小林伸一氏が選り抜いた言葉を抜き出したものらしい。“らしい”――というのは、あまりに解説が少ないので、どうにも言い切る自信がないだけである。
内容は――
「愛」「美」「暴力」「文明」「地球」「演劇」「ふるさと」「現実」「疑問符」「変身」「飛翔」「家」「怒り」「人生」「鏡」「快楽」「過去」「革命」「希望」「記録」「幸福」「言葉」「怒り」「涙」「肉体」「人間」「音楽」「女」「男」「歴史」「老人」「性」「政治」「青年」「死」「詩人」「真実」「思想」「書物」「スポーツ」「数学」「旅路」「魂」「賭博」「時」「嘘」「笑い」「私」「闇」「幼年時代」「友情」「夢」
――以上52個のカテゴリに分けて、『気の利いた言葉』が収録されている。そのうちから、私が面白いと思ったものだけ紹介してみる。
「愛」より
――自分たちにしか通じない言葉をもつのが恋人同士である。(家出のすすめ)
私はずっとこの恋人同士の言葉を持っていなかったか、もしくは相手が発した“言葉”を理解できなかったのに違いない。だから私との交際は長続きしないし、想い寄せる相手とは解り合えない。
「美」より
――美というものは、本来、何かを欠いたものです。完全な合理主義からは、美はおろかドラマも生まれてはきません。(家出のすすめ)
当たり前なんだけど、意外と皆んな忘れてしまう。忘れないために、言葉にする必要がある。
――美を何かに役立てやうなどとさもしい了見を持つのは、美のほんたうの理解者ではない。(絵本・千一夜物語)
糸井重里ね。
「文明」より
――必然ということばは社会的であり、偶然ということばは個人的である。(幸福論)
『社会的必然』は存在しても、『社会的偶然』は存在しない。
「演劇」より
――あたしたちはどんな場合でも、劇を半分しか作ることができない。あとの半分は観客が作るのだ。(迷路と死海)
その謙虚さや良し。人は謙虚さを忘れたとき、もはや人ではいられなくなる。魑魅魍魎となるのだ。大作家が突然おかしくなるのは、そのせいである。その人はもう死んで形骸だけが残り、そこに悪霊が宿って人々の眼を狂わせる。
「人生」より
――大体人生相談してくるのは、相談前にもう自分で答えが決まってるのが多い。(言葉が眠るとき、かの世界が目ざめる)
自分で答えが決まっていないと、怖ろしくてとても他人に相談なんて持ちかけられない。
「快楽」より
――悪口の中においては、つねに言われてる方が主役であり、言ってる方は脇役であるという宿命がある。
これは素直に盲点だった。常々、嫌いな相手のことを思い浮かべるのは相手の幸福のために一つ手助けをしてやっているような気分になることがある。それを決定づけられたような気がする。
「政治」より
――一言で片づけようとすれば、ヒットラーは「偉大な小人物」であった。
しかし私は、貧乏ゆすりと居眠りにあけくれて何もしない大部分の政治家が「卑小な大人物」であったことを考え併せるときに、歴史を動かしてきたのは、実は多くの偉大な小人物たちであったのではないかと思わないわけにはいかないのだ。
細心さ、猜疑心、権謀術策と権力、そういったものが不可欠な近代政治は、大人物たちには向いていないからである。(さかさま世界史)
アドルフ・ヒトラーは決して天才ではなく、究極の凡人だったのだと思う。彼の性質は生まれながらの独裁者であったが、感性は凡人中の凡人、凡百の才能のうちでも際立って平凡であった。そうでなければ、彼は画家として成功していたであろう。
「真実」より
――おかしなもので、駅と書くと列車が中心で、停車場と書くとにんげんが中心という気がする。(黄金時代)
喫茶店・珈琲屋、不倫・浮気、落語家・噺家、画家・絵描き、シナリオライター・放送作家……
硬い言葉とやわらかい言葉は使い分けたい。
「書物」より
――書物はしばしば「偉大な小人物」を作るが、人生の方はしばしばもっと素晴らしい「俗悪な大人物」を作ってくれるのだ。(時代の射手)
ルイ十六世は小人物だったが、熱心な読書家であった。彼はフランス革命が起きた日、衛兵が『革命』という言葉を使ったがために、革命の意味を知ろうと、まず書物を読みあさった。そして、ギロチンに掛けられて死んだ。
「時」より
――人は「時を見る」ことなどできない。見ることができるのは、「時計」なのである。(寺山修司の仮面画報)
時計には速度がない。同じ一秒でも、小さな時計ならほんの僅かしか動かないが、巨大な時計ならその分だけ大きな幅を動く。
「私」より
――自叙伝などは何べんでも書き直し(消し直し)ができるし、過去の体験なども、再生をかぎりなくくりかえすことができる。できないのは、次第に輪郭を失ってゆく「私」そのものの規定である。(黄金時代)
近頃はアルツハイマーに罹った画家が五年間描き続けた自画像がネット上で出回っているが、その衝撃は完全に輪郭が失われてからの方が大きい。
人は輪郭の失われたものには、恐怖するばかりである。
「闇」より
――映画館の暗闇というやつは、ときには数億光年の遠さを感じさせる。
パソコンのディスプレイで真っ黒な絵を表示する。その暗闇が不思議である。
「夢」より
――人は夢の中では覚醒時の数倍の長さの体験を持つことが出来る。
そういえば、夢での体験ほど充実した気持ちになったことはない。現実でどれだけのことを成し遂げても、その次の瞬間には酷く憂鬱な気持ちになる。
文脈が無視されているせいか、なんだか詭弁の匂いがプンプンするような言葉が多かったような気がする。虚しい言葉を前にすると、なんだか心まで虚しくなってしまった。そういう意味で、玉石混淆の本である。私なら☆3つ。
Posted at 2006/07/07(Fri) 03:04:31
文学・歴史・民俗学 | コメント(4) | トラックバック(0) | この記事のURL
この記事のトラックバックURL ->