曾野綾子『人びとの中の私』より「ついてない若者たち」というエッセイ。
曾野綾子はどうも怖くて苦手なのだが(笑)、教科書で読んだ記憶がある。
私たちが『ツいてない』という捨て科白を吐くとき、大抵それは『ついていない』のではなく、実際には当然の因果であるという。
例えば、友人に車を貸して、友人が物損事故を起こし、友人は一文無しの上、自分は対物保険に入っていない――そんなのは運ではなく、当然の帰結なのだそうな。車は凶器であり、いつでも事故を起こす可能性がある。そんなものを貸すときには、必ず最悪の事態を想定しなければならない。ある意味、物損事故で良かった――というほどのものだろうか。
また、結婚記念の真珠の首飾りを貸したら、壊されてしまった――というのも、そんなに大切なものは決して貸し借りしてはならないそうだ。首飾りという物体と、結婚記念という思い出の双方とも傷つけられてしまう。それは確かに安易に貸し借りして良いものではない。
なるほど、その通りとしか言えない。私の高校時代の教員に、若い頃は豚のように肥って、大酒を飲んだ挙げ句、肝硬変になった男がいる。それだけならただの自業自得で済むが、それを武器に、いかに自分が苦労しているか、どんな辛い闘病をしているか、ということを訴える。なすべき義務さえなさない。それで他人の同情を買おうとする。こんな人間はクズである。
本当に『ついてない』という状況は、滅多に起きない鉄道事故でたまたま事故車両に乗っていたとか、高速道路から車が降ってきたとか、本人の力や判断ではどうすることもできないことをいうそうな。先の尼崎での脱線事故などが思い浮かぶが、確かにあそこに乗り合わせた人達には何んの落ち度もない。
『運命には変えられる部分と、変えられない部分がある』――予測と努力でどうにかなることと、ならないことがある。『必要な努力をしないで、全てを運のせいに』する人がいれば、完全な努力と予測とをしていても、運だけが悪い人もいる。
面白いのは、賭け事について。競馬にしろ、パチンコにしろ、必要な努力をするからこそ、儲けを得ることができる。娯楽とはいえ、儲けを得ようとすれば、大変で、面白いものとは言えないかもしれない。
もちろん、努力することが面白ければいいが、そうでない場合はただの作業に過ぎない。それはつまり、労働と何も変わりないことを意味する。見返りを得ようとするなら、どんなことでも決して楽ではないのだ。
Posted at 2006/05/27(Sat) 10:49:46
文学・歴史・民俗学 | コメント(0) | トラックバック(0) | この記事のURL
この記事のトラックバックURL ->

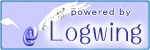
この記事へのコメント
コメント本文以外は全て入力不要です。