
私には劇場で見る機会がなかったのですが、報酬が入ってすぐDVD-BOXで購入(BDは手軽に見られなくて好きじゃないのです)。しかし観賞したあともなかなかテキストに起こすことができずに、こんな時期になってしまいました。
この作品が映画になるだけでも一読者としては、御・御・御の字です。製作委員会の皆様・監督・スタッフ・出演者・出資者の皆様に感謝。めでたく文庫も出ましたし、ぜひ再評価の流れを! バブル時代には理解されなくても、今だったら理解されるかもしれません。
こういう映画が出来るということも拝金主義の蔓延する現在においては珍しいですね。草の根的ではありますが、胸を張ることのできるしっかりした作品に仕上がっています。
さて、原作者である佐藤泰志という作家の名前は、かなりの本読みでもなかなか知らないと思います。事実某芥川賞作家の先生などは名前すら聞いたことがないという状態でして……(少々とはいえ話題になった今なら掌を返すかもしれませんが)。
一時期“芥川賞を獲れなかった”作家に興味があって、調べていたことが佐藤泰志作品との出会いです。特に興味が出たのは梅田昌志郎の繋がり(佐藤泰志デビューの選者が梅田昌志郎で、後に佐藤泰志が国分寺の辺りに住まうのもまた梅田昌志郎の影響です)なのですが、先生とは今でも手紙のやり取りくらいはしています。先生曰く佐藤泰志を評して『ごまかしばかり』とのことでしたがはてさて……。
純文学というのは現在では芥川賞を未獲得の新人が単行本を出したところで、商業など名ばかり、アマチュア漫画家の方が発行・売上部数も利益率も上なんてことはザラです(というよりも村上春樹のような存在が特例中の特例)。
当時の佐藤泰志作品の発行部数はわかりませんが、恐らく収入は相当乏しかったのではないかと思います。――尤も奥さんの方は真っ当に稼いでいましたけれど(それはそれでプライドが傷つくでしょう)。
では映画について。
端的に言うと、いわゆる函館のご当地映画となっています。
やるせなく、鬱屈した話ばかりで、劇中でずっと地面を覆っている薄汚い残雪は象徴的です。
佐藤泰志は元々映像的な書き方をしていますが、群像劇として巧く整理・脚本・昇華されており、なかなかの佳作に仕上がっているのではないかと思います。
さて、今はもう2010年代です。この時代でありながら1980年代当時の世界を表現しようというのです。この間、いかに我々の生活が変貌したか。その隙間を埋めるのは大変なことだったと思います。そして過去を表現する以上は、作品がただのノスタルジックに収まってしまう可能性もあります。
全体的に漂う昭和の映像にはセット臭さも違和感もなく、なかなかよく作ってあるなと思います。走っている車は現行車でアンマッチしている部分は仕方ないですが……。1980年代のカクっとしたデザインは現行車にはありませんね。
演技については、竹原ピストルさんの演技というか持っている物がいいですね。誤魔化しではなくご本人の素でぶつかってきている感じが良かったです。
最も印象に残ったシーンですが、足指を潰すシーンが小説でも映画でも共に記憶に残っています。そこでチンピラから施して貰う傷テープがサビオなんですよね。
ついでに社会的なことを書くのであれば、行き詰まった地方の人々の姿がありありと描かれており、80年代でありながら、まさに2014年の姿を象徴しているとも言えるでしょう。他人事ではありません。
現在の経団連や政府の目指す理想像は『1%の富裕層のために99%の奴隷が犠牲となる社会』で、民衆も相互扶助よりもどうにかして自分だけは勝ち組に入ろうという発想になっていますから、ある意味で当時よりももっと酷いかもしれません。
海外では民衆は自分たちを貧民の側だと思って行動し、裁判でも企業vs民衆という構図がたびたび生まれます。しかし、なぜか日本の民衆は、自分が貧者の側にあるにも拘わらず、自分が企業側や資本家側の立場にあると勘違いし、周囲を見下そうとする方向に走りがちです。
労働者がストライキを決行したところ、民衆側が労働者側を責めるというとんでもない事態まで発生しました。春闘でごたつく場合、民衆の敵は必ず企業であるという根本的な原則を忘れてはいけません。80年代は懐柔されることはあっても、まだギリギリでそれができていた。今や自分の都合だけで行動する人々が増え、団結するということがなくなったのですね。
そういったことを踏まえて観ると、底辺を描く映画というものはサクセスストーリーよりもずっと大事なものと思えます。
Posted at 2014/11/22(Sat) 17:39:05
文学・歴史・民俗学 | コメント(0) | トラックバック(0) | この記事のURL
この記事のトラックバックURL ->

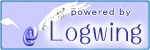
この記事へのコメント
コメント本文以外は全て入力不要です。