シュテファン・ツヴァイクといえば「マリー・アントワネット」や「人類の星の時間」など伝記作家として有名で、一般的なスタイルの小説は、現代ではあまり知られていない。
オーストリッチであるツヴァイクは二度の世界大戦で、戦禍の中心にあったが、兵士として戦争に参加することはなかった。最終的には南米へ亡命し、絶望のあまり自殺した。
ツヴァイクはヒューマニストで「一つのヨーロッパ」思想を持っていたが、現在のEUとは少し違い、ボーダーレスに近い形の理想郷的世界観だった。
典型的な、金持ちのボンボンが道楽で書き始めたタイプの作家といえる。それゆえに彼のヒューマニズムは打たれ弱く、(例えば積極的に貧しい人々に働きかけるようなことはなく)あくまで知識人や紳士同士の付き合いに限定されるものだった。
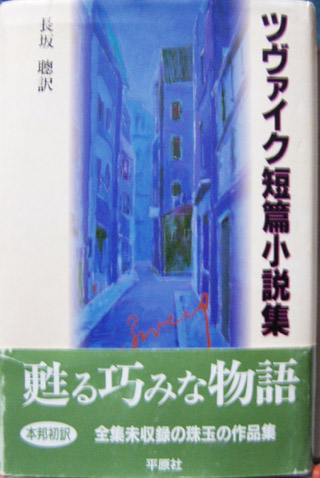
amazon.co.jp;「ツヴァイク短編小説集」長坂聡訳
ツヴァイク全集では手に入らない短篇も載っているが、初版は非常に誤字脱字の多い本だった。
「猩紅熱」
この主人公は現代のヒキコモリやオタクなどと通じるものがある。
こういう書き方をすると誤解されるかもしれないが、現代になってこうした人達が突然現れたのではなく、単に言葉が発明されて存在が明確に区分けされるようになっただけのこと。
ヒキコモリもオタクもニートも、文明発生とほぼ同時に生まれた階級制や奴隷(農奴)制などにより、比率にすればむしろ昔の方が現代よりも、趣味と遊びだけに生きた人間は圧倒的に多かった。
話しを戻そう。
田舎から都会に出てきた主人公のベルガーは都会での生活に戸惑い、大学にもなじむこともできない。医者の卵で頭はいいクセに軟弱で据え膳も食えないような男である。
すっかりひきこもって毎日妹の写真を眺めながら過ごしているある日、下宿先の少女が猩紅熱という伝染病に罹って死にそうにしている。
少女を看病するうちに医者を目指す決意を固めるが、彼女が眠っている間にキスしてしまったために自分が伝染病に罹って死んでしまう。
因みに少女の年齢は十三歳。まだロリコンという言葉のない時代のお話。
「エーリカ・エーヴァルトの恋」
今度は全く空気の読めない自意識過剰女が主人公。
最愛の男性からプロポーズされたのを自分で蹴っておきながら、全てを自分の都合良く解釈して後日密かに逢いにいくも冷たくあしらわれるという話。
しかもこの主人公、自分の非には全く気づいていない。
音楽の天才同士のカップル、というモチーフを巧く使っているので、かなり軽減されてはいますが、冷静に物語を振り返ると、もう痛いのなんの。
ツヴァイクは現代に生まれなくて本当に良かったと思う。
「駄目な男」
ギムナジウムでダブッてしまった主人公が教師に噛み付いたあと、自殺するという話。
現代で言えばただのDQN。
「昔の借りを返す話」
女性が書いた手紙体の作品だが、ちょっと要約が難しい。
簡単に言えば、昔は売れっ子だったのにすっかり落ちぶれたオペラ歌手の誇りを僅かながら取り戻してあげるという話。
実は主人公は少女時代に憧れのあまり、この歌手と肉体関係寸前まで行って、破滅の人生を覚悟したことがあったけれども、無傷で帰してもらった。
借りとはそのときのこと。
「置き去りの夢」
愛よりもお金を択んだ女性が「あのときああしておけばなー」と後悔する話。
「十字勲章」
ナポレオンの時代。
敵地スペインにあるフランス兵が一人、本隊とはぐれてしまい、奇蹟的に本隊とでくわすものの敵兵と間違われ射殺される。
しかも大事に持っていた十字勲章を見て、味方のフランス兵から暗殺者と間違われ、さらなる暴行を加えられて道端に捨てられる、というもの。
「リヨンの婚礼」
フランス革命当時、叛乱を起こしたリヨンに対して、叛逆者の処刑と建物の破壊が命ぜられたが、虐殺のために集められた地下室に、偶然にも『流血の日』に婚約予定だった一組の男女が居合わせた。そこには司祭もいたために、無事に婚礼の儀を行うことができ、二人は無事に初夜を迎える。
翌朝、死刑執行の行列にも拘わらず、一行はいかにも陽気そうに歩いていた。このまま奇蹟が起こるかと思えたが、しかし一人残らず殺されてしまった。
私はこれが一番面白かった。
参考:
wikipedia;ジョルジュ・クートン
リヨンへの派遣
1793年5月30日、彼は公安委員会のメンバーになり、8月には反革命的な行動をとったリヨンへの派遣議員となった。都市の包囲を強固なものにするため、国民皆兵の制度を整えた後、6万の兵員を集めてリヨンへ出向した。リヨンは10月9日に降伏するが、公会は都市の破壊を命令した。クートンはその命令を実行することなく、反革命指導者を適度に罰して対応したが、公会は彼の代わりにジョゼフ・フーシェ、コロー・デルボワらをリヨンに派遣し、その後彼らによってリヨンの破壊は徹底的に行われた。
「ある破滅の物語」
プリ侯爵夫人の伝記。プリ侯爵夫人はルイ15世の親族ブルボン公の愛人で、事実上フランスの国政を牛耳って金銭をたんまりと使い込んでいた。
さらにポーランドに恩を売るため、王にマリー・レクザンスカを嫁がせた。
こんなことをしていれば当然叩かれるわけで、司祭から追及されたために追放しようとして逆に自分がノルマンディーへ追放された。
そこで27歳で死ぬまでの様子が書かれている。
これも面白かった。
ツヴァイクは創作小説だとテクニックばかりに頼っているので、やはり伝記でこそ実力が発揮される
「森に懸かる星」
高嶺の花のマダムに対して惚れてしまったウェイターが、マダムの乗った列車で鉄道自殺をする話。
ストーカーもここまでやれば愛なのか?
「レポレラ」
ドン・ジョバンニに出てくるレポレラのような、気持ち悪い女従者の話。
主人はこの従者を気味悪がりながらも、都合良く気が利いているために利用していた。レポレラというあだ名までつけて。
しかしだんだん歯車が狂ってきて、このレポレラ、主人のために要らぬ人殺しまでしてしまう。主人は喜ぶどころか、心底気味悪がる。
これは怖い。
世にも奇妙な物語か、Y氏の隣人辺りにこんな話しがありそう。
こうやってあらすじに要約してみると、筋そのものはかなりえげつないものが多く、しかも登場人物で主役を張っているのはほとんどが人格障害者。しかし緻密な描写によってどうにか作品の域にまで高めている。
ツヴァイクは面白いのだけれど、繊細すぎる。
Posted at 2007/04/13(Fri) 04:00:42
ブック・レビュー | コメント(0) | トラックバック(0) | この記事のURL
この記事のトラックバックURL ->

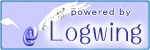
この記事へのコメント
コメント本文以外は全て入力不要です。