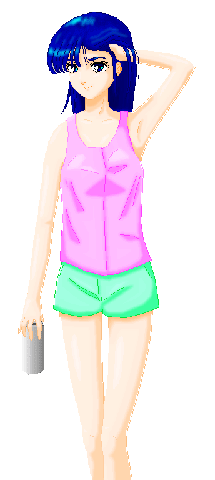
スリガラス越しに、明りが見えた。
淡いオレンジ色したその光は、白いタイルで覆われたバスルームの中に満ち、その中に立ち尽くす白い裸身を照らし出す。
その手がシャワーのコックをひねると、白い湯気を立ててお湯が降り注いだ。
「ふふん、ふんふ〜ん♪♪」
鼻歌を響かせながら、彼女はお湯を手に受け、少しづつ身体にかけてゆく。
なだらかな肩のライン、形のいい張りのある胸、細くくびれた腰のライン、程よく引き締まった尻、そしてすらりと伸びたカモシカのような足、どれをとっても文句無しのスタイル……。
だがそれは、美しさよりもを力強さを誇示していた。
「……ん〜、もうちょっと締めた方がいいかも」
みどりは鏡に自分の姿を映して一人ごちる。
「ま、よしとしよう!」
そういってシャワーを止め、バスタオルを手にした……。
みどりはタンクトップにトランクスといういで立ちでダイニングに現れた。手にはビールの缶。
「あ〜気持ちよかった!」
彼女はそう言ってテーブルについた。そうしてビールの缶を開けてぐいっと呑む。
「んっんっんっんっんっ……ぷっはぁぁぁあ!!くうぅぅぅぅ、最高!!!」「……あのなあ」
そのとき、ダイニングに眼鏡をかけた男が入ってきた。
「あ、お兄ちゃん、お帰り〜」
「お帰りじゃないだろが」
みどりの兄、将介は呆れ顔で椅子に座った。
「まったく……風呂上がりにビールなんて、親父じゃあるまいに」
「ま、お固いことはいいっこなし!」
滝沢兄妹は今2人暮らしをしている。両親はそこそこ有名な考古学者なのだが、一年中を世界を飛び回っているのだ。
「そうそう、今日美紀ちゃん達のクラスに転校生が来たの。けっこうかわいい双子の女の子よ」
「あん?また転校生か?」
「ついでに……事件もね」
肩をすくめるみどりに、将介は険しい表情で答えた。
「それは聞いている。一緒みたいだな、全く」
「でももっとふしぎなことが……」
そういって彼女は、美紀が目撃したことを話した。
「……すると、その由魅って子が手をかざすと、死人の顔が安らいだっていうのか?」
「どう、ふしぎでしょう?」
みどりは目を輝かせながら言った。将介はその目を見返しながら。
「それは……何かあると考えていいのかな?」
「多分ね。今日会って話をしてみたけど、なにかを背負っているような感じがしたわ。特に由魅って子……何かを押さえ付けるような、そんな目をしていた。哀しかったわ、なんだか……」
そこで話を切ると、みどりは一口缶に口をつけた。
「由莉って子の方は、なんだか無理に強がってるみたいな感じね。由魅ちゃんを守ろうとしてるのはわかるんだけど、つぱっちゃってるっていうのか、堅いのよねえ。涼君に送らせようとしたら断るんだもの」
くすくす笑ってみどりが言う。
「ま、送らせはしたけどね」
「そりゃなんとも典型的だな……非常にわかりやすい」
将介は大学で心理学を専攻している学生だった。そのそも将介が乙夜学園在学中に ”ILRO”を設立したのも、心理学に興味があったからであり、人物観察の場としてILROは存在していた。その後を継いだのがみどりである。
「手かざしか……しかし、なぜ死人に?」
問いかけるように将介は呟いた。
「さあ?まだ死んでなかったのかしらね?」
「由魅って子がしたことは、魂の平安を与えたって事じゃないのかな?魂は、死んだ直後ではまだ肉体を完全に離れてはいなからな」
「あら、大学じゃそんな事まで教えてくれるわけ?」
みどりが皮肉っぽくいうと、将介は神妙な顔つきになって答えた。
「いいや。彼らには目に見える物だけが全てな連中だからな。彼らは、人が想像するものが”存在”し得ることに気付かないでいる……それともあえて目を逸らそうとしているのかな?」
「違うでしょ。肝っ玉が小さいだけよ。科学だ何だと言いながら、一番非科学的なのは奴等の方じゃないのよ」
「まあな」
将介は苦笑して。
「しかし……人はいつから自分の感覚を信じなくなったのかな?未知なるものへの恐怖……見えざる物に対する畏怖の念……」
「はいはい、おしまいおしまい」
あきれたようにみどりが言うと、残りのビールを一息で飲み干した。
「まったくもう……オカルトサークルじゃないんだからね、うちは」
「だがな」
諭すように、将介は指を立てて言った。
「もうそんなことは言っていられないぞ。彼女達の出現がそれを示している。それに……」
「それに?」
「……俺のニュースソースを信じるならば、世界中で原因究明の動きが出ているらしい。表裏両方でな。詳しくは直純君に調べさせたらいいさ」
そう言って彼はメモをみどりに渡した。
「まあ、ほんと、けちなんだから。教えてくれたっていいじゃないのよ!……でも、自分で調べてなんぼだからねえ……」
みどりはそのメモに目を通すと、そばの壁にかけてあったコードレス電話を手にした……。
涼とマンションの入り口で別れた由莉と由魅は、エレベーターで13階まで上がると、自分達の部屋に向かった。
「由魅、いい?あんな奴についてっちゃ駄目よ!」
由莉は諭すように言った。涼のことを言っているらしい。由魅の方は随分と落ち着いたような表情で言った。
「でも……面白そうだよ」
「あー、もう!ああいうやつに限って二股かけたりするんだから……」
などと言い合いながら彼女達が部屋の前にやって来たとき、そこに乙夜の制服を着た男子生徒が待ちかまえていた。
「……遅かったな」
「あ、あんた……どうしてここに?!」
由莉は由魅をかばうように前に出ると、その男、木島隆を指さした。
「わかっているはずだ。君たちの行動は全てつつぬけだということは」
隆はゆっくりと歩いて由莉の前に立った。
「そして、僕が常にそばにいるということも」
「ふん!別にいて欲しくなんかないわよ。さっさとそこどきなさいよ!!」
由莉が由魅の手を引いて彼の前を通りすぎようとするが、彼は道を開けなかった。
「ちょっと!!」
由莉がにらみつけるが、隆はまるで動じず、冷静な口調で言った。
「……逃げてばかりいては解決にならんぞ。それがわからないお前じゃあるまい」
「うるさいわねえ!!あんた達が追いかけまわすのをやめればいいじゃないのよ!!」
「お前達の追跡を止めないのは、わかっていることだろうに……」
「く……」
「由莉、止めて……」
それまで黙っていた由魅が声をかけた。
「こんなとこで……やり合ったって、どうにもならないよ」
由魅は隆の方を向いて、じっと彼の目を見つめた。
「お願いだから、今日は帰って……もう少し考えたいの……」
隆はしばらく由魅を見つめていたが、すっと、二人の前に道を開けた。
恐る恐るといった感じで二人はその横を抜けようとしたが、由魅が隆と交錯したとき、隆が呟くように言った。
「……お前自身の意思はどうなんだ?」
由魅は立ち止まると、隆の方を振り返った。
「いつまでも人の影に隠れていることは出来ない……いつかは独り立ちしなけりゃならないんだ。そして……”奴等”はそれを待ってはくれない。どうする気だ?」
「……そんな」
胸の前で手を組み、戸惑いの表情を浮かべる。しかしその目の先に見えるのは、拒絶するかのような、彼の背中だけだった。
「僕には忠告しか出来ない……」
そう隆は言い残すと、歩き出した。
「あ、あの……」
由魅は思わず手を伸ばそうとして、それを躊躇した。
その間に、隆の姿は闇に喰われてしまったかのように消えてしまった。
その後を呆然と見つめる由魅……。
「……由魅、入ろ」
由莉は由魅の肩を後ろから抱いて言った。由魅は力なくうなずくと、とぼとぼと歩き出した。
「ねえ、秀ちゃん」
美紀は隣に座る秀一に話しかけた。
ここは彼女達の家のそばの公園で、小さいときは、よく涼や直純と一緒に遊んでいた。しかし、今は多少意味合いが違ってきている。
「なんだ?」
「あの双子、どう思う?」
「どうって……かわいいとは思うが……」
「ばか……」
美紀は頭を抱えると、立上がって秀一を見下ろした。
「どうしてそーゆー観点でしか見れないのよ!!まったく、これだからあたしの苦労が絶えないのよ……」
「いーじゃんか、かわいい子をかわいいと言って何が悪い!」
ばきっ!!
胸を反らして開き直る秀一を、美紀はしばきたおした。
「いてー!な、なにをする?!」
「おしおきよ、おしおき!!」
意味も無くポーズを決める美紀。
「大体、こんなかわいい子がそばにいるっていうのに、なんなのよ、その無視するような態度は?!」
「な、なんだあ?……あ、もしかして、お前、妬いてるんだろ……」
めりぃ……
今度は美紀の拳が秀一の顔面にヒット……これは痛い。
「よくも……そんなデリカシーの無いことが言えたものだわね」
「……おまえの、僕に対する仕打ちの、一体どこにデリカシーがあるって言うんだ?」
慣れているとはいえ、今日の攻撃は強烈だった。さすがに嫌みの一つも言いたくなる秀一であった。
「命があるだけでもありがたく思いなさい!……で、どう思う?」
「かわいい……じゃなくって!!」
美紀の凄みの効いた視線に、慌てて言い替える。
「なんか僕たちより知ってそうな感じはするなあ……」
「でしょでしょお!?あたしにはぴーんときたのよねえ、ぴーんと!」
腕組みして、うんうんと美紀はうなずく。
「由魅ちゃんの手かざしを見たときもそうだったけど、すんごく落ち着いているのよね、彼女達。絶対、なんかあるよ。それから気が付いた?」
「なにが?」
「木島君が……保健室まで来てたの」
得意げに言う美紀に、つまらなさそうに秀一は答えた。
「ん、まあな……」
「なんだ、知ってたの。……彼も怪しいと思うなあ。だって有り得る?二日連続で転校生が来て、三人ともが同じ場所に現れた。……それも、あんな事件の合った場所で。偶然だなんて言える?」
美紀の真剣な表情に、秀一も同じ目つきで言った。
「みどりさん流に言うなら、偶然なんか有り得ない、ってことになるんだろうけど」
「だとしたら……だとしたらよ」
美紀は、自分で自分の両肩を抱いた。
「やっぱり事件の裏には、なんか怖いことがあるんじゃないかなあって……そんな気がする……」
「……美紀」
秀一は立上がると、美紀身体をそっと包み込むように抱きしめた。
「秀ちゃん……」
「……まあ、そんなに考えすぎるなって。どうしようも無くなったら手を引くだけさ。そこまで義理は無いと思うし……」
「……でも、それはちょっとやだなあ」
美紀は秀一の顔を見上げながら言った。
「やっぱり、最後までやり遂げたい。中途半端じゃ、ね?」
「……そう来ると思った」
秀一は笑って、美紀の頬に手を添えた。
「一緒に頑張ろうな」
「うん……」
そうして二人の顔が近づき、その唇同志が触れそうになったその時。突然、二人は背後から声をかけられた。
「いい気なもんだな、ええ!?」
「うわ!!」
「きゃあああああ!!」
慌てて二人は離れると、声のした方を向いた。
「人が言い付けを守って帰ってきたら、いちゃついてやがるし……あー、やだやだ」
「もう!涼ちゃんたら!!せっかくいいムードだったのに!」
「え、えっと、あの」
美紀は膨れっ面して怒っていた。秀一はと言えば、あちこちに視線をとばしている。かなり慌てているらしい。
「こっちはなーんもいいこと無しなんだぜ。……なんで足を踏まれなけりゃならんのだ?」
「どーせ、気を悪くさせるようなこといったんでしょ?」
「一緒にデートしない?って、由魅ちゃんに声かけただけなのに?」
「それよそれ!」
美紀は涼を指さして言った。
「由莉ちゃんは由魅ちゃんの保護者みたいな立場だから、狼から守ろうとしたのよ」
「ああそっか……なんて罪深いんだろう、俺って……」
目を閉じて、自己陶酔の世界にのめり込む涼……
「将を射んとせば、まず馬を射よって言うからなあ。明日こそは……なあ、美紀……ん、ああ?!」
涼が目を開けると、そこに二人の姿は無かった。人気の無いところに移動するつもりなのだろう。
「……ちぇ。どうしてあんなのを好きだったのかねえ……」
涼はため息をつくと、家の方へと歩きだした。
「それがなんで秀一の野郎なんかに……ま、もうどーでもいいけどぉ〜」
独り言を言いながら歩いてゆくと、十字路に差し掛かった。この四つ辻に、彼らの家があるのだ。
そのうちの一つ、直純の家の方を見ると、彼の部屋に明りがともっているのが見えた。
「……今ごろなにやってるんだろうなあ。ま、どうせ小難しいことやってるんだろうけど」
ファンが空気をかきだす規則正しい音が、部屋の中を静寂にかすかなノイズを与えていた。
部屋の広さは8畳程で、パイプベッドとクロゼットが一つずつ壁際に置かれていた。そしてその反対側には、机が幾つか、それもOA机のごついのが並べられており、その上には、何台ものPCやWSが置かれていた。机の下の方にも、フルタワー型のPCが置かれている。
SUNのWS、PC98や自作らしいAT互換機……その間にディスクアレイやUPS、プリンタ、スキャナのような周辺機器が置かれている。
そして、34インチはあるCRTモニターの前に、この部屋の主、秋田直純は座っていた。
その画面上にはウェブブラウザのウィンドウが開かれ、様々な情報を表示していた。それに対し、彼はマウスとキーボードを駆使して、それらの情報を操っていた。
一般家庭には過ぎるこれらの設備が、直純だけの力で揃えられたのでは決してない。それは、この家庭の特殊とも言える事情があった。
直純の父親は現在NTTの研究所に働いているコンピュータエンジニアであり、かつてはアメリカのARPAプロジェクトに関わった事もある人物で、真の意味での”ハッカー”の生き残りであった。
そんな彼が帰国後始めたことは、自宅に専用線を引き、今で言うLANを自前で組むことだった。当時はNTTは無く、また開かれた通信などというものは、その概念すら無かった頃である。当然のことながら、他人からは理解されずにかなりの時が過ぎていった。
それでも彼は諦めず、新しいハードウェアを入手し(アメリカ時代の知人関係が役に立った)、ソフトウェアを導入して機能の拡張を行った。
その行為は次第に認められるようになり、NTTの設立とそれに伴う通信自由化が追い風となって、彼はこの分野に置けるパイオニアと目されるようになった。今直純が使っている設備は、その努力の結果がもたらしたものなのである。
そんな父親の影響をもろに受け継いだ直純は、その十分すぎるほどの素質もあって、今では父親以上にシステムを使いこなせるようになっていた。そしてその能力は、ILROに入ってから存分に発揮されていた
「……今日の事件に対するリアクションは無しか。そうだろうなあ」
直純は眼鏡をいじりながら呟いた。
今彼がのぞいているのは警察庁のサーバーだった。近ごろのブームで大分数が増えていたが、内実はお寒い限りで、警察庁のサーバーも、街頭に張られるポスター以下のものだった。
「これじゃ三鷹市役所以下だよな……」
そのとき、机の上のコードレス電話がなった。これまた今はやりのPHSの端末である。
「もしもし?」
『はーい、調子はどうかな?』
「あ、みどりさん!」
直純はうれしそうな声で言うと、マウスから手を離した。
「駄目ですね。さっぱりですよ」
『はぁ〜、さっぱりさっぱり』
「………」
『………こほん』
みどりは気まずそうに咳払いを一つした。
『えー、興味深い情報が手に入ったわ。兄貴経由なのがくやしいとこだけど』
「へー、なんです?」
『インターネットのアドレスよ……非公開のね』
「はあ……しかし、よくもまあそんなもの見つけてきますねえ」
直純はあきれたように言った。
『あたしも良く知らないんだけどさ……じゃ、言うよ』
みどりの読み上げるアドレスを直純は書き留めると、それを見て首をかしげた。
「あれ?これって、大英博物館に割り当てられたIPだなあ。どうしてこんな所に?」
『あたしが知るわけないでしょ!』
怒ったようにみどりは言った。
『それから、パスワードがいるんだって』
「どんなですか?」
『……”DELPHI”だって』
「”DELPHI”?……面白ろそうですねえ」
『やっぱりそう思う?』
もし二人が直に話していたら、お互い顔を見合わせてにやりとしたに違いない。現に、直純は、裏に隠された意味に気付いたような、にやにや笑いを浮かべていた。
”DELPHI”とは、ギリシアの地名であり、かつては太陽神アポロンを祭った神殿があって、神懸かりになった巫女が”神託”を下すという言い伝えのある場所であった……。
『なにはともあれ、このニュースソースにアタックあるのみよ』
いかにも面白そうにみどりが言った。
『でも十分に気を付けてね。なにが起こるかわからないから』
「はい、わかってます」
『じゃあ、結果は明日学校でね』
そう言い残して電話は切れた。
直純は電話機を置くと、しばらくじっと画面を見つめていた。
「……さてと。どういう経路で入り込もうかな?」
マウスをちょんちょんとつつきながら考え込んでいた直純だったが、方法が決まったのか、一旦ブラウザを終わらせると、エディタを立ち上げ、猛烈なスピードでタイピングを始めた……
今日も不夜城と化すのだろうか、この部屋は。
いや、サイバースペースには昼も夜も無いのだ。あるのはただ流れるデータと、それを取り込もうとする、飢えた狼の群れだけなのだった……。
第12あかねマンションは2LDKが基本構成であり、何室かは3LDKになっていた。由利と由魅が住むのは、3LDKの方である。
家賃は20万近くに達するだろうこの部屋に、女子高校生が二人だけで住んでいるというのは、かなり異常な事だった。親の遺産でも相続したとでも言うのだろうか?
その広いリビングには、フローリングの床の中央にソファーのセットが置かれており、そのソファーに、ガウン姿の由魅が一人、ぽつねんと座っていた。
お風呂上がりなのか、ほんのりと肌が上気している。手にはオレンジジュースの入ったグラスが握られていて、それを所在なげにもてあそんでいた。
「あ〜、いいお風呂だった!」
そこへ同じくお風呂上がりの由莉が入って来た。Tシャツに短パンという姿の彼女は、タオルで髪をぬぐいながら由魅のそばにやって来た。
「どうしたの、由魅?」
心配そうな表情でのぞき込む由莉。
「由莉……」
由魅は顔をあげた。今にも泣き出しそうな目が由莉を見る。
「……あたし……また……声を出すことも、身体を動かすことも出来なかった……」
「由魅……」
由莉は由魅のとなりに腰掛けると、そっとその肩に手をおいた。
「あんな奴のどこがいいのよ?あんな威張り腐った奴、とっととくたばればいいんだわ!」
「やめて由莉……やめて……」
由魅は身体を震わせ、目を閉じた。
「どうしてなの……どうして肝心な時に何も出来なくなるの?いつだって……いつだってそうなんだもの……」
グラスを握り締める手に力が入る。グラスは震え、中のジュースがこぼれ出した。
「あたしがもっとしっかりしていたら……あたしにもっと力があったら……」
「由魅、止めなさい!由魅!!」
由莉は彼女の手からグラスを奪い、両肩を掴んで激しく揺すった。
「そうやって自分を責めたって仕方ないでしょ?!由魅は全然悪くないの!悪くないんだからね!!」
その激しい口調に、由魅は大きくその目を見開いた。
「もうそんなこというの止めなさいよ!……あたし……そんな由魅、見てらんないよ……」
由莉はうつむき、肩を震わせた。泣いているのだろうか……。
由魅は身体の力を抜くと、自分の由莉の肩に手をかけた……その時。
『!!』
二人の身体に電撃のような衝撃が走った。恍惚感にも似たその感覚は、二人の全身に、その細胞の隅々まで、そしてその魂までも覆い尽くし、それは果てしない意識の拡大をもたらした。
二人の意識は今や一つとなって、虚無の空間に漂っていた。
……見える。
二人の声が重なり、波紋のように空間を満たしてゆく。すると、薄闇のような霧が晴れ、一つのビジョンが現れた。
荒野であった。黄色い土で覆われ、乾いた風が舞う。断崖絶壁が周囲を覆い尽くし、まるで閉じ込められたような圧力感が感じられた。
どんよりとした雲に覆われた空に、何やら黒いものが幾つか飛び交っていた。それらは次第に大きくなっていき、その姿がはっきりしてくる……
全体の形は人のようであった。その背中には蝙蝠の羽のようなものが生えており、その浮き上がった骨の先には、鋭い爪がついている。そして頭に当たる場所には……
……あれは?!
やはり!!
そう感じた瞬間……二人の意識は再び停滞の中に落ち込んでいた。
ゆっくりと目を開けると、自分と生き写しの顔がそこにあった。
「……やっぱり、あいつだったんだ」
二人の言葉がシンクロした。先ほどの弱気な姿は無かった。
「すると……」
「”ゲート”が、開きかかっている……」
二人は頷きあい、立上がって互いを見つめあった。
「……由魅、どうする?」
由莉が心配気な顔になって訊く。
「今の感じだと、もう時間が無いみたいだけど……」
由魅はまた不安気な表情になった。それほどまでに心の傷は深いのか……。
「わかんない……けど、このままじゃ、いやよ」
胸の前で手を組んで、由魅は目を閉じた。
「このままじゃ……」
由莉はその姿をただ見つめることしか出来なかった……。
「……星辰が動くか」
木島隆は星空を見上げながら呟いた。
都会の明りに侵食されつつも、その星々はきらめいていた。
と、その中を、一つの流星が流れ堕ち、そして消えていった。
「時間が無い……猶予はないんだぞ、由魅」
彼は後ろを振り返って、双子の住むマンションを見据えた。
その表情はさっきまでの落ち着き払ったものとは違い、焦りの成分が混じっていた。
「この地が、きっかけとなってくれればいいが……」
彼はそう呟くと、マンションを背にして歩きだし、そして、闇の中に吸い込まれ、消えうせる……