
クオリティとは?
多くの賢者がそれぞれ異なった「クオリティ」の定義を行っている。以下は、その一例にすぎない。
「クオリティは使用に耐えうるかどうかという適合性のことである。」(J.M.ジュラン)
「クオリティとは、顧客の要請や要求への合致である。」(フィリップ B・クロスビー)
「クオリティの違いは、望ましい要請や属性の量的違いとなって現れる。」(ローレンス・アポット)
「クオリティは心でも物質でもなく、その両方とは全然別個の実体を持ったものである。たとえ品質やクオリティの定義づけができないとしても、それが何であるかは誰もが知っている。」(ロバート・バーシッグ)
「優れたクオリティと劣ったクオリティのものとの相違は、その卓越性の度合いにおいてはっきり表れる。クオリティは、だらしのない、また嘘偽りのあるものに満足していることを排し、最高の水準のものを追求し、達成することである。」(バーバラ W・タッチマン)
もちろん、これらのどれが正しいかを議論するつもりもなければ、その必要もない。クオリティは、たんに製品やサービスの質をいうことばでもなければ、またそれらを生み出す過程のことだけを言っている言葉ではないことだけは分かる。むしろクオリティは、文化そのものととらえるならば理解しやすい。
一方、ISO9000規格での品質の定義は、「明示または暗黙のニーズを満たす能力に関する、ある”もの”の特性の全体」(JIS規格)としている。「サービス」もしくは「製品」の属性に限定していると解釈する必要があろう。すなわち、フィリップ B・クロスビーの定義そのもである。これはすでに時代遅れの定義である。耐久性とか堅牢性などのような製品やサービスの健全性にのみ限定する時代は終わっているからだ。クオリティは、たんに物理的、外在的、あるいは目に見えるかたちのものでなく、もっと奥深い文化的な性質をいう。
各国の文化が異なると同じように企業や個人の文化は同一であるはずがない。同じくクオリティは、創成する人や場によって違いが出てくるのは当然であり、しかるにクオリティの相対的優位性を相互に高める競争が発生する。もっと穏当な言葉を使うならば、クオリティを「磨く」行為は、国、企業、そして個人の各レベルでの自然発生的現象とも言える。古代美術のすばらしさは、それを物語っている。ニューヨークのメトロポリタン美術館にあるエジプト時代の建築物や絵画を見るとき、人間は進歩したというが本当にそうかと疑問に思うことがある。エジプト古代美術から感銘を受けるその高度さは、まさに自然現象的行為の結果がクオリティであることを証明している。
クオリティの性質のもう一つの側面は、クオリティが文化的であるからと言う理由で定量化できないものであってはならいことである。むしろクオリティは何らかの手法で物理的に測定、もしくは検量されなければならないと定義すべきである。さもなくば、人や社会によるクオリティの「所有」そのものが不可能となる。経済活動の中でのクオリティを語る場合「所有」できないものがクオリティであるならば、クオリティは必然的に人や社会に対して無用なものになり存在の価値がなくなるという論理の矛盾が生じる。「所有」が個人の段階で留まるならばこの論理矛盾はない。したがって、クオリティは測定可能なものである。
1970年版のウエブスター(これは私の宝物)には、クオリティとは、「よし悪し」と決められるモノの属性であるとしている。「よし悪し」は人間しか判断できない。したがって、この概念は「顧客」があってこそのクオリティであることを暗示し、クオリティは顧客の目によって決まるという決定的な性質を保持する。クオリティ自身は、何らの実用的な機能を待ち合わせていないが、それが顧客の望むモノであるときにその存在が認められるという特性がある。この考えが「顧客満足」の基本的理念であり、ISO9000規格の精神であるとだけここでは指摘するにとどめる。
日本でも米国でもクオリティの話をするとき必ず出てくるのがTotal Quality Management(TQM)やデミング賞である。この講座は、ISO9000規格の示唆する品質マネージメント・システムを議論するのだが、これらとISO9000の関連づけをしておきたい。下図に示されているように、ISO9000は、米国の軍規格の上位にはあるが、世界で卓越したクオリティを求めているものではない。特に、「日本経営品質賞」の生みの親である「マルコム・ボールドリッチ賞」に比べ、ISO9000の要求している品質システムは、大きく隔たりがあり、低い位置にある。
近年欧米では、世界企業の中での競争力を強化するために、「ベンチマーキング」という手法が多用され、技術力はもちろん流通、情報活用など経営に関わるすべての面で手本となる企業と比べて、自社の力がどの程度であるかを評価し、絶えず世界一流を目指すことが一般的になってきている。日本の企業のように「横並び」指向で経営の品質を測ることなど考えてもいない。ISO9000規格が、いま日本でもてはやされているのは、またもやこの「横並び」指向を示すことなってしまった。
ISO9000そのものを卑下しているわけではない。ISO9000は、上図でわかるように国際規格以上でもなければそれ以下でもないと明確にその位置づけをすることが必要であると強調したい。すなわち、品質マネージメント・システムとはいえ、経営の質を高める面でいうならば限界があることを認識してほしい。やはりそれ以上に位置する高度なシステムへの第一歩でしかない。しかもTQMは、限りない継続的改善の積み重ねであり、これでよいという限界はないと言える。クオリティには、そんな性格もあると言うことでもある。
現在のISO9001規格は、1987年に制定され、1994年に改定された。現規格も2000年末ごろにはさらに改定される予定である。規格は、企業が顧客に対し顧客と「契約」したとうりの製品やサービスを提供できるように20の切り口で企業内活動を分解し、各々の活動において守るべき基準を定めている。その最初の活動項目が、「経営者の責任(Management Responsibility)」である。規格で使われている日本語による「経営者の責任」と同じく、英語の「Management Review」も必ずしも規格の意味することとが適切に表現されているものではない。規格の意味することは、モノやサービスの品質を維持・向上させる上で経営の最高責任者が担う役割を明確にしたものである。
品質方針
経営責任者がまず行わなければならないのは、自社の事業を発展・向上させるためになくてはならない「クオリティ」に関する経営方針である。経営方針そのものは何らの価値もないが、経営方針を「定める」過程に大きな意味がある。2000年版ISO9000規格では、つぎのように述べている。
「効果的で効率のよい品質システムを構築し実施する上で、経営者の経営理念と方針は絶対に必要となる。また、経営トップは、顧客満足を高めることともに、他の利害関係者、すなわち株主、社会、従業員、供給者などに対しても有益である組織にしなければならない。したがって、経営トップは、はっきりと目に見えるようにリーダーシップを発揮し、利害関係者の満足を満たすための方向付けを打ち出さねばならない。」
この内容から明らかなように、経営責任者は、改めて事業の見直しを行い、自社の顧客が持っているニーズや期待を再確認する過程が必要となる。この過程を通じて得られた顧客情報の集積と理解が重要なのであって、経営方針は単純で明解なものであればよい。たとえば、以下の例である。
「お客様の信頼と満足を得る」
品質目標
経営方針が決定されたなら、その方針を達成するための品質方策をつくる作業に入る。2000年版ISO9000規格では、「これらの品質活動計画の策定にあたっては、安全性、潜在的なP/L上の責任にも配慮し、人的な面、顧客、あるいは環境へのリスクを低減するための方策をも考慮の一つとしなければならない。」また、「幅広い意識をもって企業を取り巻く環境の変化を関知し、活動計画を定期的に見直す必要がある。」とし、この方策作成には次のような視点からの配慮が必要と示唆している。すなわち、
部品などの供給者と共に価値づくりを行える関係を創設する
品質方策は、企業の業務分野や規模によって大きく異なるのは当然だが、実行可能性と緊急性を考慮し、中長期的と短期的な観点から具体策のいくつかを選択する。この方策が決まれば、規格が要求する「品質目標」は容易に作成できる。しかも、「クオリティとは?」の講座で述べたように、「クオリティは何らかの手法で物理的に測定、もしくは検量されなければならない」ということが、ここで具現化されなければならない。したがって、以下の事例のように、その達成度を測ることができるような文言が「品質目標」には使われる。
工程内製品不良率を半減する
責任と権限
たとえ品質目標が明確になったとしても、管理職を含む社員が「何が自分の役割なのか」が分からなくては、質の高い業務は達成されない。たとえば、靴の販売店員に「靴を売れ」と言えば、靴は売れるかも知れない。がしかし、お客様に質のよいサービスをさせることはその彼からは期待できないと同じである。そこで規格は、経営責任者は組織の責任と権限を明確にしなければならないとしている。特に、日本企業の場合、責任と権限をあまり明確にしないことや一般職と専門職との区別をさける社会的風土がる。このために、組織の要員の責任と権限を明文化するこの作業は困難を伴うときがある。
また、責任と権限の明確化は、組織の柔軟性を弱め事業運営の妨げとなる考えを持つ中小企業経営者もいる。しかし、この考えは捨てた方がよい。なぜなら、責任と権限はいつでも経営責任者が変更できるからである。一旦決めた責任と権限は変えられないと考えること自体が柔軟でないと指摘したい。欧米企業では、責任と権限は新しい業務につくときにはかならずあり、その内容はメモ一つで変えるのが日常的に行われている。部長職が、重役の役割を任せられることも、特別プロジェクトのリーダーに任命されるのもメモ一つである。この方式の方が柔軟性があると指摘する。少なくとも、最初に明文化された責任と権限があると、「それは私の仕事ではないとかあるとか」いう悶着は起こらない。
責任と権限が決まれば、それぞれの組織に対して人、モノ、金に関わる「経営資源」をどうするのかを決めることになる。これらはすべて有限であるから、そのバランスをどうとるかが経営責任者の役割である。とは言え、規格で要求していることは、「経営資源」を最適配分した結果を組織図で示すことだけで、それ以上のことは求められていない。ISO9000規格の限界はここでも現れている。
さて、日本企業がISO9000品質システムを導入するに際して組織の組み替えを行う場合が多い。たとえば、今までなかった品質保証部とか品質保証室を新設するなどがそれである。規格は、企業にこのような新規の組織をいっさい求めていないことに注意してほしい。企業組織に一つの機能を加えるのではなく、組織全体が品質保証のレベルを高める継続的活動に参画することが規格の要求事項であることに留意してほしい。特に、新設された品質保証部門に品質システムの運営を任せてしまい、それで認証取得の目的が果たせたと思うのは、経営責任者の認識不足で企業業績の上で最悪の事態となりうる可能性がある。なぜなら、品質システム自体が本来の意図から乖離し、「無駄の創成システム」に変身するからである。
現行1994年版規格は、品質管理責任者の任命と経営責任者による見直しに関する規定の文言をここで記述することになっているが、2000年版では、次項の品質システムに移行されている。よって、本講座も2000年版に従って進める。
2000年版規格は、品質システムを「品質方針を具現するために必要な組織構成、手順、プロセスおよび経営資源を統一したものであり、利害関係者に利益をもたらすものでもある。」であると定義している。企業目的の中でもっとも重要な「利益」という言葉を使っていることに注目してほしい。1994年版規格では、企業業績に関してはいっさい言及されていないために品質システム導入のメリットが見えてこないという欠陥を包含している。一方、2000年版では明確な表現で企業利益につなげるマネージメント・システムであるとしている。
では、経営責任者は、利益向上のために「すばらしく機能すると共に効果的な品質マネージメント・システムを構築する」に当たっては、何を行わなくてはならないのだろうか。2000年版は、企業環境の要素に焦点を合わせて以下のような視点から品質システムを構築し、運営、維持しなけれならないとしている。すなわち、
顧客のニーズと期待を満足させる製品とサービスを提供することを通じて
これで明らかなように、品質システムは現時点で世界の企業が目指すべきマネージメント・システムであると言える。(参照ページ:品質マネージメント・システムのプロセス・モデル )しかも、環境マネージメント・システムの併合も容易となり、企業運営の「質」を高めるための米国国家品質賞、「マルコム・ボルドリッチ賞」へ上る階段の第一段であることは明確である。と言うと、そんなに高尚なシステムは、中小企業には必要ないと反論する経営責任者もいないとは限らない。だが、これらの目標をすべて完璧に果たす必要があるとは規格は決して要求していない。継続的な改善・向上を可能にするしくみを求めているだけである。自社の現状、実力や規模などを考慮した品質システムであればよいだけである。容易な表現をすれば、「志は高く、身丈に合った品質システムを」と言っているにすぎない。ここを誤解したために、「重厚」な品質システムを構築し、自らの首を絞めている企業もあるやに聞いている。中小企業にはそれなりの品質システムがあり、背伸びをする必要は必要ないことを強調して次に進める。
品質マニュアル
文書化された品質システムが「品質マニュアル」である。品質マニュアルの性格としてもっとも重要なのは、公開性である。すなわち、企業の利害関係者である顧客、株主や地域住民に自社の品質システムがどのようなものであるかをいつでも示すことができるという点に特異性がある。そのための文書化であることを理解すれば、ニュアルの内容をどの程度詳細に記載すればよいかが判断できる。企業の社内規定などは、一般には秘密文書、すなわち非公開を前提に作成される。したがって、外部を意識することなく業務の詳細まで記述することが多いが、品質マニュアルでは重要なプロセスの要点のみを文書化するに止めることが肝要である。ちなみに2000年版規格では、以下のように述べている。
「品質システムに記述する業務手順の適用範囲と詳細さは、業務のタイプと複雑さ、利用している手法、そして従業員が業務を行う上で必要となる技能と教育訓練の程度によって定められるべきであり、一概には言えない。
品質マニュアルは、単純であり、明白で、しかも理解しやすく記載されねばならない。一つの業務手順をどの程度詳しく記述するかは、品質マニュアルで用いられている文言の詳細さにより変わりうる。」
品質管理責任者
経営責任者は品質システムの実質的オーナーである品質管理責任者を任命することを規格は求めている。この品質管理責任者は、「他の責任に関わらず下記の事項に対して明確に規定された権限を持つひとりのメンバー」である。
1.品質マネージメント・システムの構築、実施、維持を行う責任
これらの役割から理解できるように、品質管理責任者は、品質に関わるすべての活動に責任を持って対処する経営責任者の代行人である。今までのように付随的役割しか持たされていなかった品質保証部長や兼務で品質管理を任されていた技術部長などとは、性格が一変している。すなわち、組織のすべての部門を横断的にマネージする独立した業務である。この役割を持った責任者を組織にすえることが、品質システムのもうひとつの特徴であり、これがよろしく機能しない場合にはISO9000品質システムは、事業業績には貢献しない単なる形式面での補強に止まる危険性を包含してる。よって、品質管理責任者は、従来型の思考方法や社内慣行にとらわれることなく、広い視野からの観察、分析、発見、検証、提言を経営責任者に行うことを志すべきである。
ISO9000とTQM
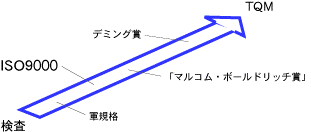
経営者の責任
「品質第一、次工程はお客様」
「安全第一、最高品質、環境保護世界のために」
従業員の意欲を高める
社会的な要望・期待に対して敏速に対応する
株主への利益還元を向上させる
品質方針と関連する達成目標を明らかにする
人、モノ、資金、情報の経営資源を適切に配分する
定期的に品質達成度を見直す
継続的な改善の風土を育てる
将来を見据えた組織構築計画(経営の変革)を立てる
顧客苦情を年間10件以下にする
下請け企業の品質指導を年2回実施する
品質に関わる社員教育計画を達成する
社員改善提案件数を月2件以上を達成する
出荷伝票作成間違いを前年実績の50%以下とする
電話ベル3回までに誰かがでる
年央および年度実施末顧客満足度調査の総合評価で7.5以上を獲得する
品質システム
顧客満足の向上と維持に努める。
組織が期待に沿って運営されている確固たる自信を株主に与えねばならない。
従業員個人の効率と効果を向上させることのみならず、従業員が仕事を通じて
満足感を味わえるようにする。
協力企業との関係が両者にとって有益であることを目指す。
地域社会と環境の両者に対するニーズに注目する。
効果的で効率的な組織であること。
すべての業務が効果的かつ効率的であることを確かめることができる
プロセスがある。
業務および製品の品質改善プログラムを設立し、実施する。
さらに、潜在する、あるいは実在する品質問題を明白にし、その予防策と是正処
置を講じる
2.品質目標と達成度の進捗状況の監視と報告
3.改善すべき案件と機会の提言
4.顧客苦情を含む品質に関わる顧客との関係に関する監視と報告
5.内部品質監査の運営
6.明文化されていない顧客のニーズと期待の収集