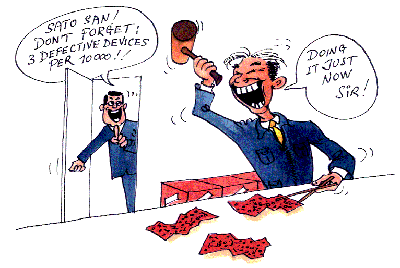情報化投資を急ごう
定年を迎えて暇を弄ばせていたときに、経営の質を問うホームページを作ろうと思ったきっかけを作ってくれたのが、日経新聞の「大磯小磯」欄であった。この欄を担当する記者は、経済や経営の専門家であろう。しかも、たいへん優れた方達である。さて、けさ(10月末日)も賛同したくなる話題を提供してくれた。
「この不景気に投資の話しはないだろう」と思うかもしれませんが、社長、まあ聞いて下さい。米国では空前の好況を謳歌してきましたが、これは情報化投資のおかげと言う人がおおいのです。90年代に入って本格的なパソコンとインターネットの時代が来たそのときに、あちらでは年々20%増という勢いで情報化投資が行われ、今や民間設備投資の中で情報化投資の占める比率は45%になっているそうです。米国では情報化投資の限界利益率はそれ以外の投資に比べ十倍以上だというデータもあるようです。
「何でも米国のまねををする必要はない」とおっしゃいますが、情報化投資だけはそうはいきません。研究開発の短縮、資機材調達の最適化、生産の合理化、流通の効率化など企業の存立にかかわる課題は情報化投資に関係するのです。特に、最近は企業と顧客、消費者をコンピューターで結んでその選好を即時につかみながらそれを企業活動に反映させていくことがすごく重要になってきました。
客の注文をとって服を仕立てたり、パソコンの注文生産はもう常識です。自動車のモデルチェンジだってコンピューターを使って周到に市場調査を行えば、今のような当りはずれがなくなります。印刷業や広告業だって消費者がどんな情報を望んでいるかつぶさに把握していれば随分効果的なPRができます。私も情報システム担当者としてライバル企業に先をこされたらと心配でなりません。
「だからこれまで情報化には相当資金をつぎこんだが、その割りには効果があがらないじゃないか」。ええ、当社は確かに情報システムとしてはかなり立派なものが整っていますから追加資金は余り要らないかもしれません。必要なのはこれにふさわしい組織作りと業務プロセスの革新です。権限委譲、分権化で意志決定を迅速にすること、チームワークを良くして総合力を発揮できるようにすること、社員教育を徹底して情報への感度を高めることが大切です。
最近流行のCIO(情報統括役員)も置いて当社の情報戦略の責任と権限を明確にすることも忘れてはなりません。け経営戦略での対応と相まって情報化投資の効果は倍増します。何しろこうして社長のところに伺うのに部長、坦当取締役、副社長を経なければならないのでは情報は腐ってしまいます。
読んでまず気付くことは、この一文の中には2000年版ISO 9004の「品質マネージメント・システムの八つの原則」がほとんど入っていることである。特に、組織作りと業務プロセスの革新はISO 9000そのものである。また、パソコンとLANの構築など情報化投資を行ったとしても、その技術を生かすことができるノウハウの開発や従業員の教育がなくてはその力を発揮することはできない。そんなことを反省するのに役立つ一文であった。
企業統治(コーポレート・ガバナンス)とパブリック・リレーション
2000年版ISO 9004や環境マネージメント・システムでは、組織のすべての利害関係者とのコミュニケーションを必要条件としている。一方、日本社会を見渡すと、日本企業の企業統治(会社はだれのものか)のあり方が問われている。そこで企業のPR(パブリック・リレーション)の重要性はますます高まっている。朝日新聞のウイークエンド経済の欄で取り上げられた真田 照三氏のインタビューの答えを引用して、これからのパブリック・リレーションのあり方を考えたい。
宣伝は、例えば「おいしいコーヒーはいかがですか」と、一方的に言うわけです。これに対して、相手の会社に伺って「今度こんなおいしいコーヒーが出たんですよ」と説明する。相手は、「僕にはちょっと苦すぎる」と答える。こういうツーウエイ・コミュニケーション(双方向の会話)によってし相互理解を深める、これがPRです。
欧米でなぜPRが発達しているかというと、小学校から授業でディベート(討論)をやっていますね。「あなたのいうことは分かる。しかし、私はこうなんだ」と。でも日本人がこれをやると、けんかになっちゃう。次第に声が高くなって「その言い方はないだろ」とか。日本では、そういう意味で双方向の会話がしづらく真の意味でのPRが難しい。
企業はPRの重要性を認識すべきだと指摘されています。
企業統治とは、企業が活動する上で株主や従業員、取引先、地域社会などとに基本的な関係をどう構築する、という概念なんです。日本では昨年来、企業のトップが直接、間接に関与する不祥事が相次ぎ、この言葉がしきりに使われるようになったんですが、ポイントは、だれがどうやって経営をチェックできるか。たとえばアメリカでは、株主が経営者を常に監視していて、社長でさえ無能だったら首にしてしまう。
PRは、企業統治を実現するためのコミュニケーションのあり方全般を考えようというものです。アメリカでは株主と経営者、社員が三つどもえになっていて、企業はまず株主に対し、状況はこうこうだ、といつも説明しているわけです。従業員に対しても同じです。日本の場合には、株主に年二回ほど簡単な営業報告書を出しておしまい。その辺の違いなんですね。
では、日本の企業はどうPRすべきだと。
企業統治で一番必要なのは社内を固めることです。それには社内広報を徹底すべきです。どの会社にも社内報はあると思いますが、読んでいる社員は10%もいませんよ。役員から新入社員まで読むんだから、社内報も三つか四つに分けて、それぞれの目標にあったものを作るべきです。
日本の金融危機への政府や業界の対応ぶりをPRの視点で見ると?
日本では「以心伝心」が美徳とされていますよね。心とは、正直で隠し事がないことだと思うんです。最近、その場限りのウソが多すぎます。危機管理というのはウソをついちゃいけないんですよ。問題があったたら、その場で「申し訳ございません、これは認めざるをえません、今後一切いたしません」と。間違いを犯しながら、どうだこうだと言うから、おかしくなる。(以下省略)
どうも真田 照三氏は、神戸生まれのように思える。この語りぐちは、神戸弁そのものである。それはさておき、PRの観点からも日本企業の行動パターンは、自己中心的で国際的とはとても言えそうにない。もう少し「目線」を下げて、ISO 9000への取り組みを考えると、この欠点が出ていると言える。経営者が一生懸命取り組んでいるのに、社員が熱心でないと苦情を言う前に、分かりやすく説明できているのかを反省すべきではなかろうか。と言っている私も今週は、ある会社で一般社員へのISO 9000品質システムの説明会をする。目線を下げているつもりだがさてどうだろうか。もう一度使う資料を見直すつもりだ。
経営者のアカウンタービリティの変化
企業統治(コーポレート・ガバナンス)の話と切り離せられないのが、アカウンタービリティである。ISO 9000で言う責任と権限の関係と同じであるからだ。ここでも日経新聞の「大磯小磯」の出番である。
経営者のアカウンタービリティ(説明責任)について考えてみたい。
後半部分を読んでいると、ISO 9000規格の解説ではなかろうかとも思った。やはり、日本企業は、本当の意味の市場経済にさらされていなかったとも言える。となれば、ISO 9000の精神を経営者を含めて経営文化として定着させることは並み大抵のことではないだろう。先日、ある企業の従業員にISO 9000規格を優しく説明したが、一般社員にも責任と権限が与えられていると言ったら、「えー!」という反応があった。経営者から一般社員にいたるまで、規格が要求する責任と権限のもとで業務を行うという意識を育てることにもISO 9000の意義があると感じた。
どうして日本人の「SATO-SAN」なの?
映画評論家の淀川長治さんの訃報が伝えられた。悲しかった。寂しいと感じた。映画は、私にとって本当の娯楽である。どんな映画でも楽しい。終戦直後の日本人には娯楽と言えば映画だった。中学時代は、一人で映画館に行くことは禁じられていた私立校であっても罪悪感にかられながらこっそり潜り込んでいた。テレビが発達して、映画が「ただで見られる」と感激したことが思い出される。それ以来、テレビは映画を見る道具と定義している。アメリカにいるとき、テレビなんて見るものではないと言われたが、映画は見ていた。それも、ちゃんっとテープに撮っていまも持っている。日本に帰ってからゆっくり見たいと思ったからだ。
淀川長治さんは、神戸の三中(現在の県立長田高校)の先輩である。この日曜日の洋画劇場で元気な声を聞いたのに、その彼が亡くなったなんて信じがたいことである。人間はいつか死ぬとは理解できても、突然の出来ごとにしか感じられない。彼には、お悔やみを言う家族が無いことを知っている。だから、この一文で、彼の安らかな死を願うことにした。
とんでもないことにおつき合いさせてしまいました。本論に入りたい。けさISO事務局のホームページを見ていたら、こんなマンガが掲載されていた。ISO事務局には悪いが、ちょっと拝借させていただく。
なぜ「SATO-SAN」なのでしょうか?ISO 9000では、「きめられたことを守りなさい」と強調します。不合格品は「10,000分の3」と決まっているから、「SATO-SAN」は、わざわざ3個の不合格品を作っている日本人。みなさん、どう思われますか?几帳面な日本人。ばか正直な日本人。とんでもないことをする日本人。不合格品は絶対作らない日本人。ISO 9000はとっているけどその精神は分からない日本人。さーどれでしょうか、私にも分かりません。しかし、日本人をマンガに使っていることは、確かです。
ポーランド人のことを言う似たようなジョークがあります。電球が切れて、交換するときのことです。電灯笠が高いので、肩車をしてひとりの男が電球を交換することになりました。その男が、「みんな、電球を捩るからまわれ」と言った。下にいる3人の男は、ゆっくりと全員が回りました。
今日は金曜日です。「よい週末を!」。
株主への対応にしても、企業株主と主婦を含む一般株主とでは、報告書の書き方も変えるべきでしょう。目線を下げるというのは、ばかにしているのではなくて、分かりやすくするということです。
経営者のアカウンタービリティと言えば、コーポレート・ガバナンス(企業統治)論において、株式会社の経営者が業務執行に関して取締役会ひいては株主に対して負う説明責任ということになる。
従って、経営者には一義的には「株主利益の最大化」という観点からのアカウンタービリティが求められるわけだが、企業には株主のほかに従業員、取引先、債権者といった利害関係者が多数関与している。アカウンタービリティの内容もつまるところ現実に錯綜するこれら多数の当事者間の利害を調整したうえで、いかに株主利益を最大化していくかに重点があるということができよう。
従来型の日本的経営においては、このような利害調整は主に取引先や債権者とりわけ主力銀行、そして従業員との間で図られてきたといえる。かかる経営者においては、おのずと長年の取引慣行や企業固有の事情に対する株主や取締役会の暗黙の了承を前提とした上で、経営者のアカウンタービリティが成り立ってきた。
企業にとっての大株主は持ち合いを通じて形成された取引先や主力銀行であり、取締役やその代表である経営者は従業員の出身者であることにより、株主利益と取引先、従業員などの間で利害の調和がある程度担保されてきたという見方もできる。
しかしながら、持ち合いの解消やその受け皿としての年金基金の機関投資家などに象徴されるように、企業経営においても市場の圧力が増大する中で、好むと好まざるとにかかわらず、経営も特定の取引先や従業員を意識したものから、より市場の声、外部の不特定多数の市場関係者を意識したものに重点を移さざるをえなくなっている。こうした状況においては、経営者のアカウンタービリティも、その権限と責任をより明確化し、判断基準が外部から見て十分に評価可能なものでなければならなくなるわけである。
ただし、このようなアカウンタービリティは必ずしも経営者が市場の声に追従するということを意味しないことに留意するべきであろう。けだし市場経済において「市場の失敗」はつきものであり、経営者はこのリスクへの対応を含めたアカウンタービリティがとわれるからである。