
忠義心と裏切り
あるパソコン雑誌に、マサチューセッツ工科大学メディアラボ日本代表、バーナード・クリッシャー氏が「忠義心と裏切り」と題して興味ある論評を記載している。ISO 9000品質システムを講演するするときに、今までの日本企業の品質管理の分析から入る。その中で、終身雇用制に基づいた日本人従業員の忠誠心が大きな役割を果たしてきたが、今後はそれに期待できなくなると指摘している。同じような意見がこの論評にあるので、転載する。
私はかねてから「忠義」について興味を抱いていた。かって日本の将軍と大名、侍の関係においては「忠誠を尽くす」ことが重要な役割を果たしてきた。それは、各集団が自分たちより上位の集団に忠誠を尽くすことにより、上位の集団から保護されるというルールに支えられた関係だった。
日本では今、終身雇用という仕組みが、ひいては社会秩序までもが崩壊の様相を呈している。終身雇用もまた、社員が会社に対して揺るぎない忠誠心を持つことの見返りに、会社は社員を生涯にわたって雇用することを約束するシステムだ。「忠誠を尽くす」ことのほうが「よく働く」ことより重要だったのだ。
経済の不調がこのシステムに変化をもたらす以前には、会社員は自分の職の安定を案ずることはなかったし、会社に対して、ほとんど狂信的とも言える忠義を示していた。(途中略)
変化の激しいこの不連続の時代において、従来のこうした盲目的な忠義の態度が裏切られているようだ。会社員が、会社や職場の人間に対する不満を述べる場合も、それはだんだん欧米の企業で聞かれるようなものに近づいてきている。また、社員が他社へ寝返ったとしても、それはもはや驚くほどのことではなくなっている。
このような忠誠心の低下にともなって社員の善意を基盤にした品質管理を含むシステムは、脆弱となることは目に見えている。だから、ISO 9000のようなトップダウンの経営が必要となってきている。とするのが、私の意見である。実は、この論評には、顧客の期待が製品やサービスの供給者によって裏切られる具体的な事例があげられている。もうそれは、品質システムであり、「マルコム・ボールドリッチ賞」の中身である。
あるところで「サプライチェーンって知っている?」と最先端技術をものにする企業の重役に尋ねたら、「なんですか、それ?」との返事だったので、これは少し話をしておかねばと焼酎を飲みながら話をした。今やサプライチェーン・マネージメントを知らないでは、今後の経営は成り立たない。
定年を2ー3年前にしていたときのことである。アメリカ人の女性社員がサプライチェーンのプロジェクトに関する調査報告を日本で行った。アメリカやシンガポールの製造工場から日本の主要顧客に直接納入することによる流通コストの削減の可能性が大きいことが彼女の結論だった。しかし、これらの工場からの製品品質に泣かされた我々は余りにも危険な冒険としか映らなかった。日本での横持ち費用や再検査費用のことを考えると、費用面での合理性の高さには同意せざるを得ない。しかも、日本での一時在庫品のために資本(現金そのもの)を寝かせることは直接利益に結びつくことは重々理解できても、海外工場の品質管理に不信感を抱く日本人にはそく賛成できる事柄ではなかった。この「サプライチェーン・マネージメント」とは何ものかを知るのが今回の話。それは、次のようなことである。
「店頭の販売情報を基に、コンピューターシュミレーション技術などを使い生産計画や需要予測を精緻にする経営効率化の手法。在庫圧縮、納期短縮など効果はトヨタ自動車のカンバン方式と似ているが、情報通信技術をフル活用するのが特徴。本格的なSCMは一企業・グループの枠を超えて情報網を構築、複数の企業があたかも一企業のように動く生産・流通システムとなる。」(日経新聞)
さらに、新聞は次のように報じている。
「サプライチェーン・マネージメントに製造業が注目するのは、これまでの多品種・少量生産に加え、売れ筋商品が目まぐるしく変わる激しい市場環境に直面しているからだ。
需要拡大期の大量生産システムは、実際に売れる量を超えて生産しても過剰在庫に苦しむ企業が少なかった。しかし、現在は売れ筋商品をタイミング良く供給しないと在庫が急激に膨らむ。売れる商品だけを生産・販売しようというSCMは、大量生産システムから脱却し切れない製造業各社に幅広く浸透する可能性がある。
SCM導入は国際競争力向上の一つの手段であるキャッシュフロー重視の経営基盤づくりにもつながる。寿命が尽きた商品・市場からいち早く撤退、店頭情報などをヒット商品の開発に生かせれば、在庫の最小化と売り上げの最大化を両立できる。受注から納入までの期間短縮や設備嫁動の効率化と合わせ、資金効率を引き上げられるからだ。
SCMは90年代に入って米国で広がったが、原形はトヨタ自動車の生産方式とされる。車の売れ行きに合わせて必要な部品を在庫過剰とならないよう必要な時に調達する「ジャスト・イン・タイム」をヒントに、米国企業が効率的なシステムに仕上げた。
それが日本に逆上陸した形だが、生産現場の従業員の経験や勘に頼りがちだった日本の生産システムに対し、SCMは末端の実売状況などデータの的確な分析が重要となる。しかも社内各部門の実体に通じていないと最適な生産・供給計画は立てられない。数字に対する感覚を鋭くしたり、組織の縦割りを排するなど、従業員の意識改革が導入成功のカギとなりそうだ。」
社会経済生産性本部が発表した少々古い資料(1994年)だが、日米企業の経営品質の優劣を「マルコム・ボールドリッチ賞」のクライテリア別に調査・評価している。下図がそれである。
特筆すべきは、お客様重視とお客様満足の面で日本は米国より劣っていることと、リーダーシップの低さである。リーダーシップの低さは難なく理解できたとしても、お客様重視の低評価には同意できないかもしれない。しかし、このページでも再三指摘しているように、日本企業は供給者としての品質をお客様押し付けていた。この認識ができていないことを証明する事実は、ISO 9001品質システムの重要性を無視してきたことである。ISO 9001規格は、「顧客サイドから製品とサービスのクオリティを要求するとこうなる」とする仕組みとその実施事項をまとめたものであるからだ。では、この当時米国は、ISO 9000規格に高い価値観を与えていたかというとそうではない。彼らは、「マルコム・ボールドリッチ賞」の手法を企業運営の柱としていた。「Quality : your cutting edge」が1994年に流行った言葉であった。
一方、バブル経済に支えられた事業業績は高く、事業計画でも日本企業が優れていることが当時の評価であった。だが今日、残念ながらこの評価結果はもろくも崩れ去った。それどころか、日経新聞に、「日本企業が今とるべき姿勢は横文字だからといって、うのみにすることでも、はなから退けることでもない。大切なのはかっての米国企業と同様、相手の経営手法を率直に学び、自らに適した形で体得することである。」とまで言われる事態となっている。日米企業の優劣は、過去10年間で逆転してしまったと言いたい。
ある冬の日私たち夫婦が訪問したのは、ニュージャージー州に住んでいる昔の友達であるドン・ヘイゼルトン宅である。彼等一家と日本で一緒に仕事をしてから数年を経ていた。日本にいたときには幼かった子供達もすっかり成長していた。長女は、もう高校生だ。しばらく彼女と話をしていたが、そのうちに高校生なのに税金の還付を申請していることを知った。アルバイトで得た年間収入を申告し、「ビックブラザー」と言われる国税局から所得税の還付を受けるためであった。なんでもないようだけれど、すっかり考えさせられた。高校生時代から税金に馴染んでいるアメリカ人と一度も税務署とは関係を持たずに一生終わる人もいる日本人とでは、「権利・義務」の意識の点で大きな隔たりを生んでいるに違いないと思った。国が国民の生活を守り、国民はそのために税金を払う義務を果たすことを基本とする民主主義国家の根底が異なっているとも言えるのではなかろうか。この一点で日本では民主主義国家が成り立たないように思う。「権利・義務」の意識が薄い「甘えの構造」で成り立っているのが日本である。そんな社会の中に「権利・義務」や「責任と権限」という個人意識が果たして育まれるのだろうか。「権利・義務」は、国と国民との関係であり、「責任と権限」は会社と社員との関係であるとすれば大きな疑問を持たざるをえない。少なくとも日本は本当の民主主義が発展していない国であるとしか思えない。納税する義務を負わされた国民は、国の税の使い方にチェックを入れる権利がある。この権利行使なくしては、国が税金を正しく使うすべをおぼえることすらできないことを承知しているのだろうか。そんなこともできない国に民主国家がうまれるなどは、幻想にすぎない。
アメリカで生活するには、「Social Security番号」はかならず必要となる。これがなくては銀行で口座は開けず、クレジット会社への支払いなどにどうしても必要な小切手を発行してもらえない。日本人が受け入れている銀行口座からの「自動引き落とし」による決済はいっさい考えられない。なぜなら、クレジット会社からの請求書が信用できないからだ。請求書の中身を調べて納得できれば個人小切手をクレジット会社に発行し、精算することになる。小切手が落ちると小切手そのものが戻ってくる。これが領収書の代わりを果たし、税金の申告に使う。駐車違反の罰金も小切手を警察に送ることで出頭する必要はない。だからクレジットカードと銀行口座なしでは一日も生活ができない仕組みである。かくかくかように個人の自己責任の上に成り立ったシステムである。一方、日本では「背番号制度」による個人所得の把握に対して反対する人が多いと聞く。もちろん高額所得がはっきりされると困る人は反対するのは当たり前だ。だが、なぜそんなに大きな所得を得ていない大多数の日本人が反対するのか分からない。やはり「曖昧な世界」を好む国民なのだろう。これが、日本型社会システムが育まれてきた背景の一つであると指摘したい。その日本型社会システムには、大きな弱点があるとつくずく思うことがある。相手を信用するのは良いことである。しかし、「なあーなあー」では困る。企業は財務内容をきちんと公開しない。日銀でさえ勝手放題をやっていることが税務局に調べられている。金持ちほど税金を払わなくてもよい法律がいくつもある。このようなことが入り組んでいつの間にか日本を蝕んできたことに気付いてほしいと思う。
今回発表された経済戦略会議の中間報告では、日本型社会システムをどう捉えているかを示したい。
規制・保護や横並び体質・護送船団方式に象徴される過度に平等・公平を重んじる日本型社会システムが公的部門の肥大化や資源配分のゆがみをもたらしている。このため、各種のシステム改革によって資本・労働・土地等あらゆる生産要素の有効利用と最適配分を実現させることが必要である。
日本的含み経営がグローバルスタンダードからみて非効率化し、リスクへの挑戦を困難にしている。土地担保融資をベースとする日本型間接金融システムも機能低下に陥っている。21世紀の日本にふさわしい新しい企業経営、金融システムの構築が急がれる。
以上は、前文であり、「おわりに」と題して以下のように提言している。
ともすれば、これまでの日本の経済社会は急激な変化を嫌い、弱者保護の名の下に既得権益の維持を優先してきた結果、既存秩序の枠組みは大きく崩れず、改革の歩みは遅々としていた。しかし、経済のグローバル化や少子化・高齢化等経済構造変化が予想を上回るスピードで進行するなかで、変化に対する後追い的な対応はもはや経済の活力を喪失させるだけでなく、将来への希望も失わせかねない。1980年代前半の米国経済も双子の赤字と貯蓄率の低下、企業の国際競走力の喪失等、様々な問題を抱えていた。
しかし、小さな政府の実現と抜本的な規制緩和・撤廃、大幅な所得・法人減税等を柱とするレーガノミックスに加え、ミクロレベルでの株主利益重視の経営の徹底的追求とそれを容認する柔軟な社会システムをバックに、米国経済は90年央には見事な蘇生を成し遂げた。最近でこそ、アングロアメリカン流の経済システムの影も目立ってきているが、日本も従来の過度に公平や平等を重視する社会風土を「効率と公正」を基軸とした透明で納得性の高い社会に変革していかねばならない。もちろん、21世紀の日本が目指すべき社会は「弱肉強食」の無秩序かつ破壊的な競走社会であってはならない。それは個々人の「選択の自由」と「失敗を容認し、再挑戦が風土」に裏打ちされた真に安心できる社会でなければなるまい。(以下省略)
「過度に公平や平等を重視する社会風土」は、公平や平等を重んじるあまり責任と権限を明確にしない社会の中から生まれてきたのである。個々人の責任と権限を明らかにし、その範囲では嬉々として働き、役割を全うすることが自然に受け入れられる社会の構築に今年は期待したい。
ある理由で、 日本企業の「根っこ」にあるぜひ直したいことについて追加が必要になった。以下は、トヨタ自動車社長 奥田 碩氏と経団連会長 今井 敬氏の意見である。こんなことも含めて日本社会の変革が必要と主張する。
世界的な自動車業界の再編が進む。国際競走に伍していくには世界で人や金を活用していくためのグローバルな経営体制の構築が欠かせない。
「トヨタもそうだし、日本企業全体もそうだが、その根底にあったのは情実型の社会であり、浪花節型の社会。人やモノが国境を超えていく時代になるとそうしたものは払拭されていかざるをえない。経済合理性、すなわち資本の論理をはっきり出してやっていく時代が日本にも来る。我々はそういうところまで読んでやっている。」
日本的経営の今後をどう見る。
「日本的経営の特徴は二つある。第一は横並び。これはいや応なくやめざるを得ない。どの産業にも大手が5,6社あって、同じ行動をとってきた。これからは強弱の二極分化、ある分野に強い専門分化が起きる。各社は収益性を高めるために得意な部分に特化しなくてはならない。合併も進むが、それより商品別の提携が進むだろう。」(以下省略)
ここまでは日本型社会の悪い面を指摘してきたが、良い点もある。元国連事務次長 現在広島平和研究所長 明石 力氏は以下のように述べている。
「日本社会は横並びの行動が多すぎるが、同時に他人の存在への配慮、気遣いという特徴がある。国際会議の議長をしていると、こうした日本社会のもつ丁重さ、優しさ、折り目正しさに外国人が深い印象を受けているのを目の当たりにします。効率的な個人中心社会に変わっても、こうした点は失ってほしくない。国際人になることは決して、他人に配慮しない一匹オオカミになることではありません。一匹オオカミは国際社会でも嫌われます。自分の考えをはっきり言うのと同じく、他人の考えもきちんと聞いて、チームワークを築いていくのは、どの社会でも必要なことです。
ただその大前提としての自分の意見の表明については、日本はこれまで遠慮が多すぎた。他人と同じ意見でも、自分の表現で言うことが大事なんです。中国の朱鎔基首相が日本からの訪問客を敬遠しているという記事が朝日新聞にありましたが、私が同じ立場だったら同じように感じるでしょう。本題に入る前に余計な話が多い。講演依頼でもファックス一枚で済むのに、菓子折りを持ってあいさつに来ないと失礼だと思ってしまう。そろそろこういう風潮から卒業していいのではないでしょうか。」
サプライチェーン・マネジメント
日米企業の経営品質の優劣
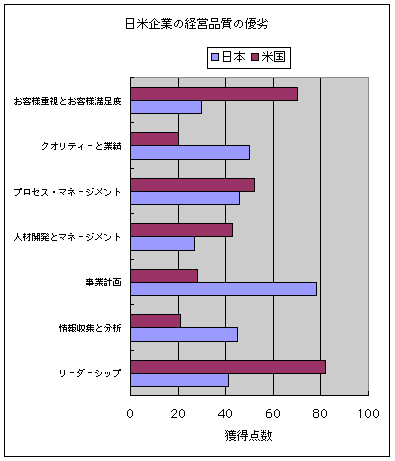
年頭に思うこと