SONY GPX−5コロンブス(VCA−27)

- SONYのハンディーナビゲーションシステムGPX−5で使われているGPSユニット部分。
- GPX−5では、本体からこのユニットを取り外して使える様に設計されていて、取り外して使うためのケースが用意されている。
- この写真は、ユニットを専用ケースに収めたところ。
- ケーブルの先は本来なら専用のコネクターが付いているが、これも可搬性を考慮してMini−DIN6Pコネクターに付け替えた。
 内部写真1
内部写真1
- これまでのIPSシリーズと違うことが一目瞭然である。
- アンテナの大きさははIPS−5000と似たような感じだが、角が取れて、8角形をしている。
- 受信感度というか衛星捕捉性というか、見かけ上の受信感度は、残念ながらIPS−3000/5000には及ばない。
 内部写真2
内部写真2
- これも、IPS同様に基板は2枚構成である。アンテナが付いている基板はRF部分であり、信号処理部分と独立している。
- 基板上にはMITSUMIのシルク印刷が確認できる。どうやら、SONY純正というより、MITSUMIからのOEMって感じがする。
- RF基板は思ったより重さがある。シールドもかなり厳重にできている。
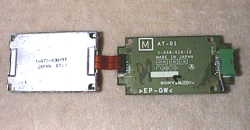 内部写真3
内部写真3
- 処理基板の裏面には部品が実装されていない、パターンとコネクターのみである。
- 2枚の基板はフレキシブルケーブルで結ばれているので、むやみに片方の基板だけを持ち上げると、ケーブルが断線する可能性が大きい。
 内部写真4
内部写真4
- ちょっとした細工です。
- このユニットはRES端子の電圧マージンが少ないため、RS−232Cレベルコンバータに接続した場合、リセットが効いた状態になり動作しなくなる。
- そこで、電源部分から抵抗を介してプルアップをかける。
- こうすると、問題なく動作する。
 専用ケースの構成
専用ケースの構成
- 部品点数は3種類4点。
- ケース本体、ケーブルそれにケーブルを止めるネジ2本。
- これらはすべて単体で注文できる。
- 専用ケース一式という注文方法は無いから要注意。
- IPS−3000/5000ではケーブルを固定するためにネジ穴がユニット本体にあるが、このユニットはそれが無い。
- ケーブルを差し込んだだけでは、簡単に抜けてしまうので、テープで固定するか、このような専用ケースで収めるのがベスト。



 内部写真1
内部写真1 内部写真2
内部写真2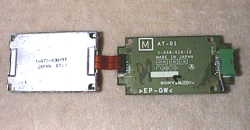 内部写真3
内部写真3 内部写真4
内部写真4 専用ケースの構成
専用ケースの構成